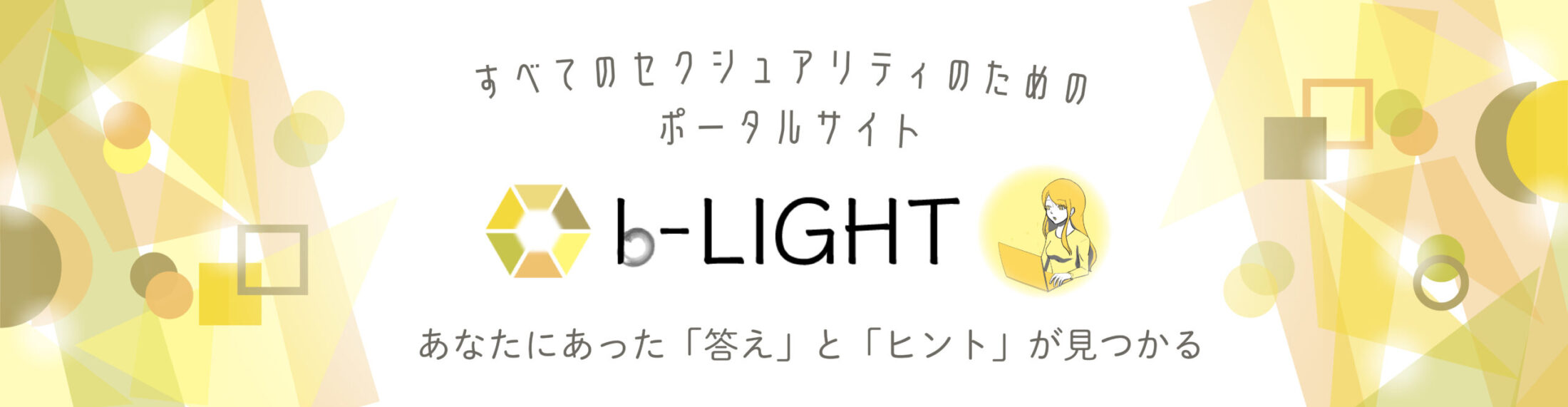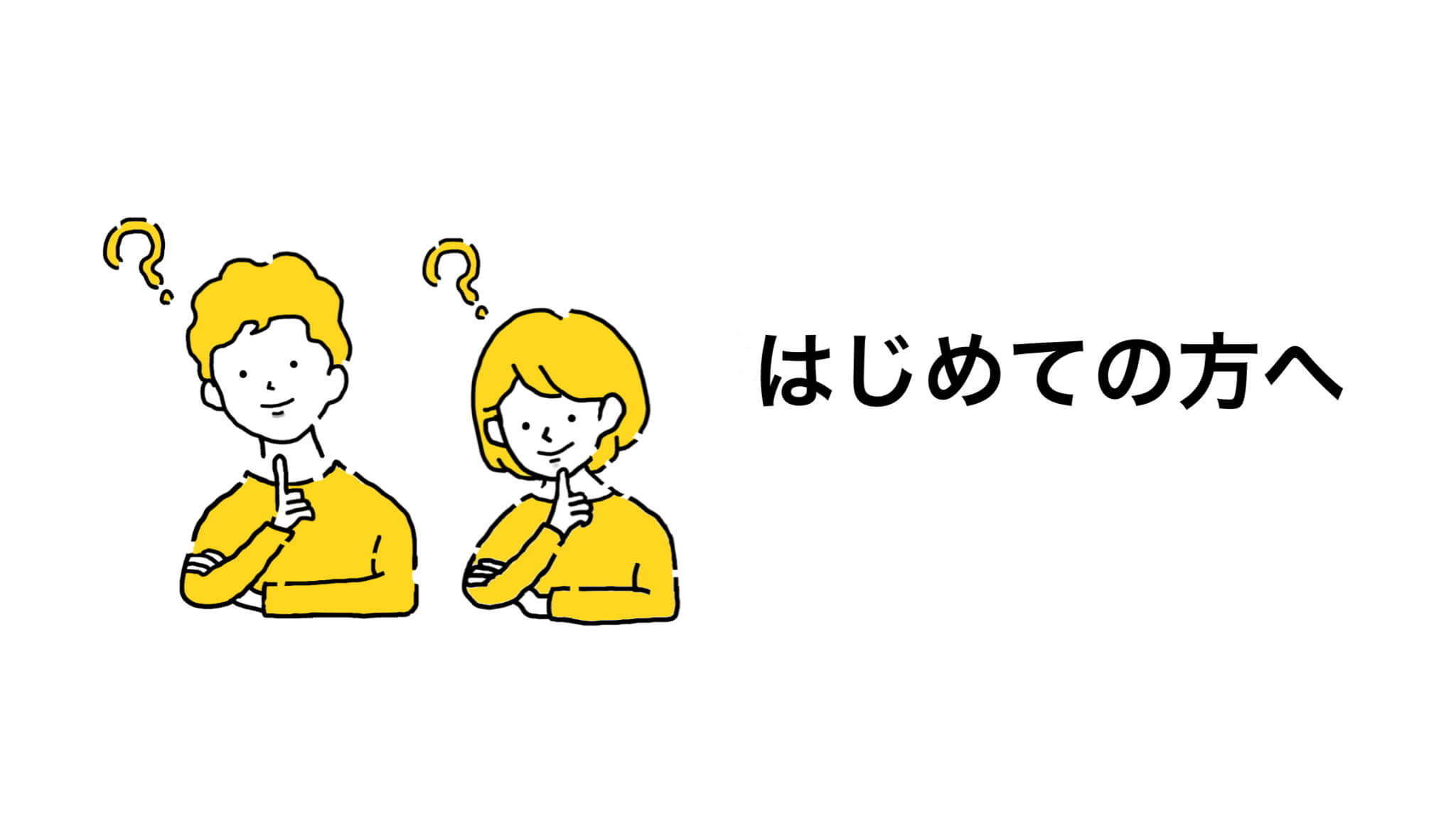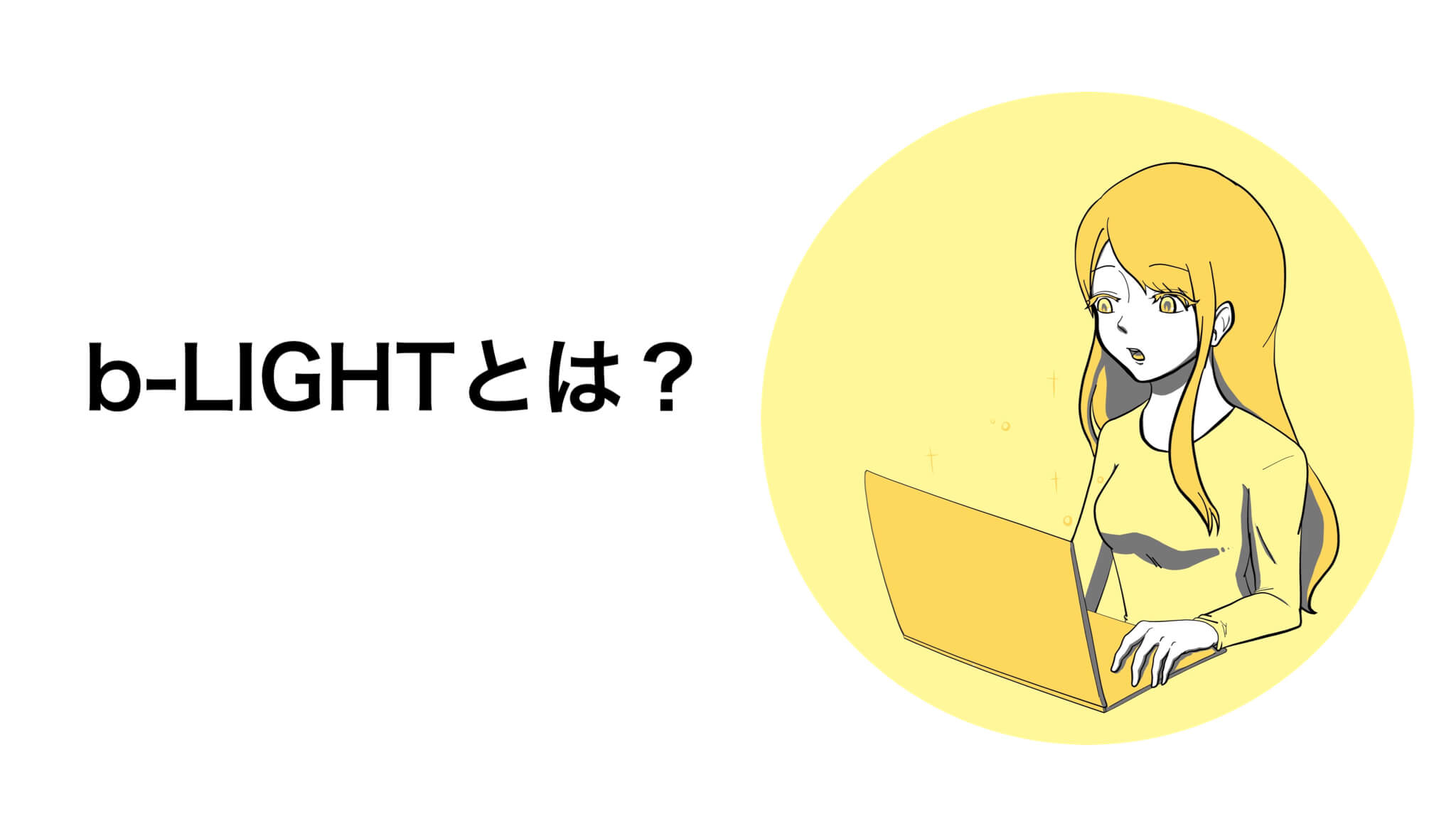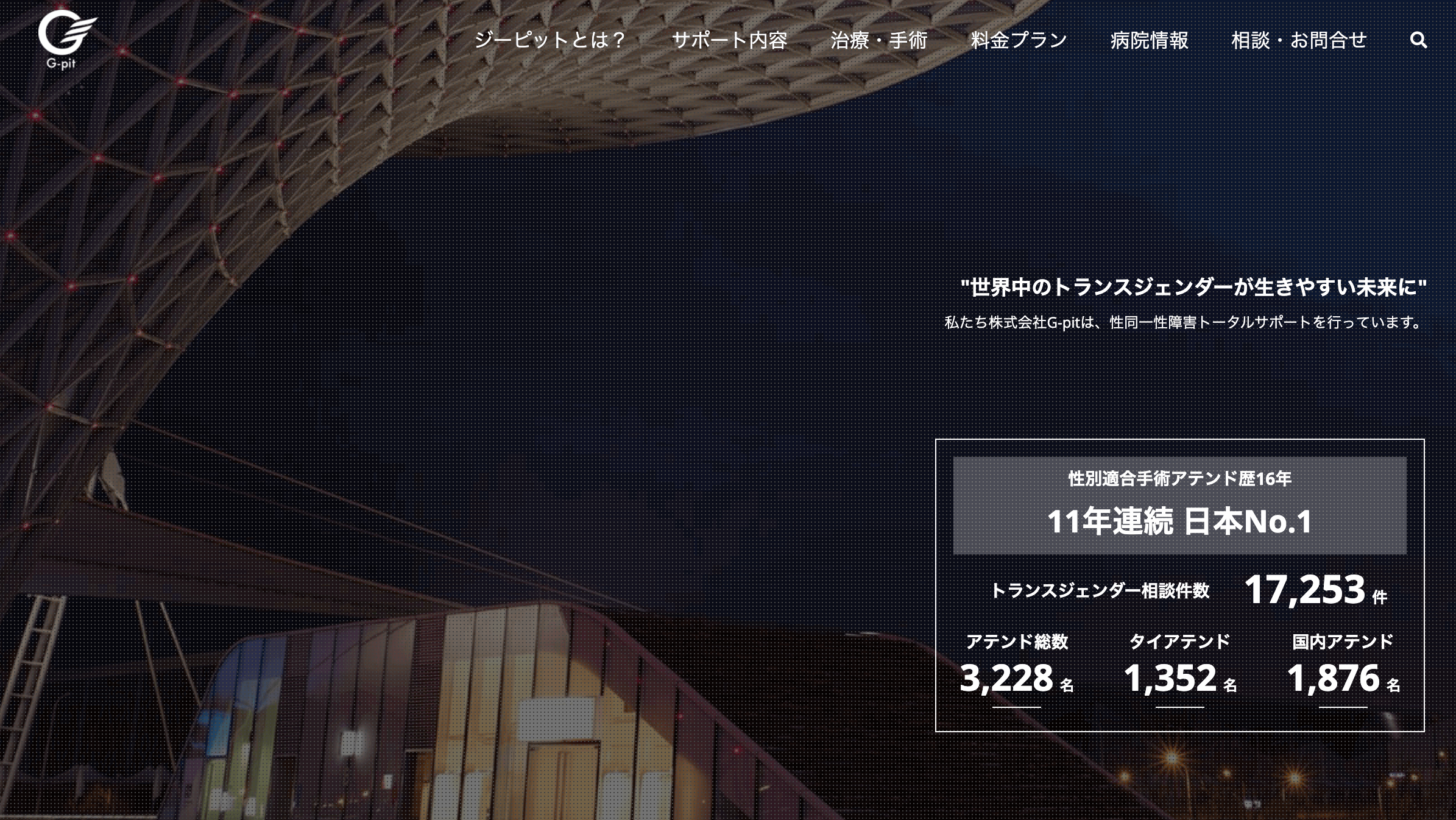みなさんこんにちは、b-LIGHTライターの號です。
今回はFtM当事者である僕の実体験を交えながら、「戸籍の性別変更をするまでの流れ」についてお話したいと思います。トランスジェンダー当事者の方もそうでない方も、
「そもそも戸籍の性別を変えるってどういうこと?」
「どんな手順で進めるの?」
といった疑問がたくさんあると思います。そうした疑問を、今回の記事で少しでも解決できたら嬉しいです。また、ここでは戸籍変更のために必要な手術や治療に+αして、どういったステップを踏んで手術を受けていくのか、僕の体験を基に解説していきます。

僕が戸籍の性別変更をしたのは2014年なので、現在とは異なる部分もあるかもしれません。
今回の記事では、下記のトピックスでまとめました。
その1~戸籍の性別変更申請の条件~
その2~籍の性別変更の条件を満たすための治療ルート~
その3~戸籍の性別変更申請から実際に性別が変わるまでの流れ~
少し長くなりますが、気になるところから気軽に読んでいただけたら嬉しいです!
その1~戸籍の性別変更申請の条件~
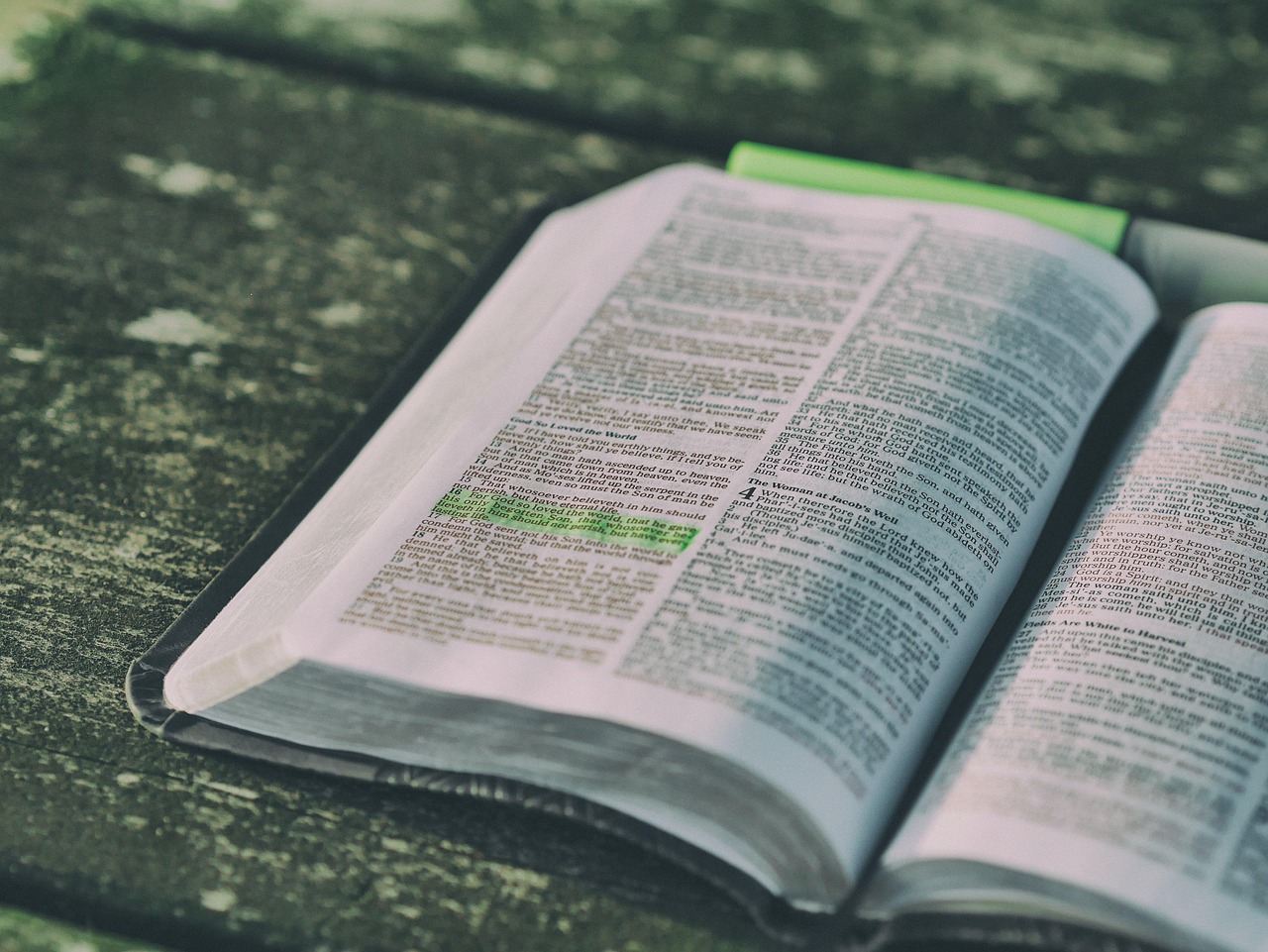
2025年現在、家庭裁判所で定められている「戸籍の性別変更を申請できる条件」は下記の6つです。

()内は僕の方で補足した説明になります。
①二人以上の医師から、性同一性障害の診断を受けていること★
(2人以上の精神科医からの性同一性障害の診断書+性別適合手術を受けたことを証明する診断書)
②18歳以上であること
③申し立て時点で婚姻をしていないこと
④申し立て時点で未成年の子供がいないこと
⑤生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること★
(FtM・MtF共に、性別適合手術により生殖腺を摘出していること)
⑥他の性別の(FtMであれば男性の、MtFであれば女性の)性器の部分に近似する外観を備えていること★
上記の項目を満たしていれば、戸籍の性別変更の申し立てが可能です。
①の性同一性障害の診断書について、家庭裁判所のWEBサイトでは「二人以上の医師から性同一性障害の診断を受けていること」という一文になっていますが、実際には
Ⅰ:2人以上の精神科医からの「性同一性障害」の診断書
Ⅱ:確実に性別適合手術を受けたことを証明する診断書
上記の診断(診断書)が必要になります。
Ⅰについては、バラバラに2通ではなく、2人の精神科医からの連名で1通用意する形で問題ありません。
Ⅱについては、国内で性別適合手術を受けた場合は手術を担当した形成外科医、タイなど海外で性別適合手術を受けた場合は、FtMであれば国内の婦人科医、MtFであれば国内の泌尿器科医から診断を受け、診断書をもらう必要があります。
僕の場合は、
Ⅰ→2人の精神科医からの連名で1通(かかりつけの病院内にいらっしゃる先生2人)
Ⅱ→性別適合手術はタイで受けたため、国内の婦人科医から1通
上記の形で診断書をいただきました。

Ⅱについては、精神科医の先生がⅠの診断書に直接「性別適合手術を受けていること」を記入して省略する場合もありますが、家庭裁判所によってはそれだと申請が通らないこともあるので、かかりつけの先生によく確認しましょう。
★マークがついている項目については、カウンセリング・ホルモン治療・性別適合手術によりクリアできます。治療を進めることにより、徐々に条件が満たされていくようなイメージです。
⑤の生殖機能の条件については、2023年10月の事例(記事の最後のまとめにて後述)がきっかけで「この要件は違憲である」という声が上がるようになり、手術をせずに性別の変更が認められる例も増えてきているようです。
しかし、まだ確実ではないため、一旦記事内では現在の条件に沿って解説をしていきます。
次は戸籍の性別変更の条件を満たすのに必要な治療について解説していきます。
・診断書は精神科医からの診断書のほか、性別適合手術を受けたことを証明する診断書も必要
・治療を進めることで条件を満たしていく
・特例も増えてはいるが、基本的には現在の要件が採用されている
その2~戸籍の性別変更の条件を満たすための治療ルート~

戸籍の性別変更の条件には、治療を必要とする項目がある点について触れてきました。
では具体的にどういった治療が必要なのかについて解説したいと思います。なお、記事内では日本形成外科学会が設定しているガイドラインに基づいたルートをご紹介します。
FtM(女性→男性)の治療ルート
まずはFtMの治療ルートについて解説していきます。

治療名うしろの()は、その治療を受けるために必要な条件になります。
A:精神科医による「性同一性障害」の診断(制限:なし)⇒戸籍の性別変更条件①を満たす治療
月に1回程度のペースで、カウンセラーによるカウンセリングを行います。病院によって診断書が出るまでの期間が異なりますが、長くても半年以内で発行されることが多いです。
B:乳腺摘出手術(胸オペ)(制限:18歳以上 ※親権者の承諾が得られれば18歳未満も可)
C:男性ホルモン治療(制限:18歳以上 ※18歳未満の場合も、医師が2年以上経過観察し必要と認めた場合は、15歳以上で開始可能)
⇒戸籍の性別変更条件⑥を満たす治療
胸をとる手術と、身体を男性に近づけるためのホルモン治療です。
胸オペは国内で単体で受ける場合(内性器摘出手術と同時に受ける方もいます)、日帰りの手術が可能です。手術直後は血を抜くためのドレーン(管と血をためておく容器)をつないだ状態で退院し、翌日ドレーンを抜きます。
ホルモン治療は、男性ホルモンを投与し、その副作用(声変わり、髭が生える、月経がとまる、肉付きが男性らしくなるなど)により見た目を男性に近づける治療になります。最初の頃は2週間~3週間に一度投与することが多いです。ホルモン治療に関しては、すべての手術が終わった後も定期的な投与が必要になります。
乳腺摘出手術(胸オペ)と男性ホルモン治療は、どちらが先という規定は特にありません。ある程度費用を抑えつつ男性らしい見た目に近づくことができるため、多くの方はホルモン投与から始められます。
また、戸籍の性別変更の条件⑥についてはホルモン治療だけで満たすことができるため、戸籍の性別変更だけにフォーカスする場合は、乳腺摘出手術は必須の治療ではありません。

僕はホルモン治療を10ヶ月ほど受けた後に、国内で胸オペを受けました。
戸籍の性別変更に必須ではないことは認識していましたが、自分のなかでは必須だったので、迷わず手術を受けました。胸オペは大学の夏季休暇中に受けました。
D:内性器摘出(子宮卵巣摘出)手術(制限:ホルモン治療1年以上、20歳以上)⇒戸籍の性別変更条件⑤を満たす治療
手術を受ける病院により条件が少し変わりますが、基本的には上記の条件は必須になります。詳しい条件は、診断書をもらうかかりつけの病院でよく確認しましょう。また海外で手術を受ける場合は、英文の診断書も必要になります。
術式や病院により異なりますが、前日を含め4~5泊の入院が必要です。タイで手術をした場合は、退院数日後に最後の診察(及び抜糸)を受け、帰国します。国内で手術をした場合は、これも病院によりますが、定期的に診察を受けましょう。
子宮・卵巣を摘出した後は、体内で女性ホルモンを作ることができなくなるため、男性ホルモンの投与が必須の身体になります。必ず欠かさないよう気をつけましょう。

僕は胸オペの翌年に、タイで子宮・卵巣摘出手術を受けました。
約12泊と長期のお休みが必要だったので、また大学の夏休みをあてました。
アテンド会社をいくつか比較し、G-Pitさんのベーシックプランに。
初めての海外、初めての全身麻酔手術などなど不安は色々ありましたが、
G-Pitのスタッフさんや同時に手術を受けにきていたFtMさんたちのおかげで、
とても素敵な旅になりました。
補足
G-pit(ジーピット)さんは、タイと日本での性別適合手術サポートや、無料相談、病院紹介を行っています。詳しくはこちらをご覧ください。
E:戸籍の性別変更
子宮卵巣摘出手術を受けると、戸籍の性別変更の条件の身体的な条件はすべて満たされます。特に「手術を受けてから●●年以内」といった決まりはないので、自分のタイミングで申請を進めましょう。
F:膣閉鎖・陰茎形成手術(制限:ホルモン治療1年以上、20歳以上)
FtMの場合、戸籍の性別変更に必要な治療はDの内性器摘出手術までです。F:陰茎形成手術は男性器をつける手術になるため、一見すると、戸籍変更条件⑥の「他の性別の生殖器に近似した見た目であること」を満たすのに必須なように思われますが、FtMの場合はB:ホルモン治療の副作用によるクリトリスの肥大がこれを満たしているとみなされるため、戸籍の性別変更をする上で、Fは必須ではありません。

僕も内性器摘出手術までで、あとはホルモン治療だけ続けている状態です。
どこまで治療をするのか、これはどこにも正解はないです。
自分の身体の違和感と向き合い、納得のいく治療を吟味していくのが何より大切だと思います。
MtF(男性→女性)の治療ルート
続いてMtFの治療ルートを解説していきます。MtFの場合はFtMのように「ここまですればOK」といった区切りはなく、戸籍の性別変更を除く場合、必ず最後まで治療を受ける必要があります。MtFの方が負担が大きいというよりは、術式の都合上治療を区切ることが難しい、といったイメージです。
a:精神科医による「性同一性障害」の診断(制限:なし)⇒戸籍の性別変更条件①を満たす治療
こちらはFtMと同じ条件になります。約半年間をかけて、性同一性障害の診断を受けます。
b:女性ホルモン治療(制限:なし)⇒戸籍の性別変更条件⑥を満たす治療
c:豊胸手術
c:のどぼとけ切除、ほか
こちらもFtMと同じく、女性らしい見た目に近づけるため、まずは女性ホルモン治療を受けます。豊胸手術やのどぼとけの切除など、女性ホルモンの効果(身体が丸みをおびる、筋力低下、胸がふくらむなど)を見ながら、自分が納得がいく身体になるため、治療を進めていきます。
d:精巣摘出・造膣手術(制限:20歳以上、ホルモン治療1年以上)⇒戸籍の性別変更条件⑤⑥を満たす治療
MtFの場合は、術式の都合上(男性器の組織を用いて造膣を行う)、精巣及び生殖器の摘出手術と造膣手術が同時に行われます。段階を踏む場合もありますが、戸籍の性別変更をする(造膣手術を受ける)場合は必須という形でまとめさせていただきます。またFtMと同じく、MtFの方が精巣を摘出した後は体内で男性ホルモンの生成ができなくなるため、女性ホルモンの投与が必須の身体になります。
e:戸籍の性別変更
以上が「戸籍の性別変更をするため」に必要な治療およびルートになります。本来であれば戸籍の性別変更はゴールではなく、治療はあくまで自分の身体の違和感を軽くしていくためのものなので、自分にあった進め方や治療を選んでいきましょう!
・ガイドラインの治療のなかには戸籍の性別変更に必須ではないものもある
・必須の治療はFtM、MtFで少し異なる
・治療の順番や内容は本人の体質や、何に違和感を感じるかで選ぶ
・性別適合手術の後もホルモン治療は継続して行う必要がある
その3~戸籍の性別変更申請から実際に性別が変わるまでの流れ~

治療を経て戸籍の性別変更条件をすべて満たした後、ご自身が住まわれている地域の家庭裁判所で戸籍の性別変更の申請を行います。ここからは、申請をしてから実際に戸籍の性別が変更されるまでの流れを紹介します。

戸籍の性別変更の申請からの流れは、FtM、MtF共通です。
戸籍の性別変更の申請
(1)居住地の裁判所へ、戸籍の性別変更の申し立てを行う
申し立ての条件を満たしたら、まずは家庭裁判所へ「戸籍の性別を変えたい」という申し立てを行います。必要な書類は下記の通りです。
~性別変更の申し立て必要書類~
・申立書・・・1通
・出生時から現在までのすべての戸籍謄本・・・1通
・性同一性障害の診断書(Ⅰ2人以上の精神科医からの診断書+Ⅱ性別適合手術を証明する診断書)・・・それぞれ1通
※別の病院の精神科医からもらう場合はⅠを2通、Ⅱを1通)
申立書は事前に裁判所のWEBサイトからダウンロードが可能です。裁判所でもらい、その場で記入することも可能です。書類に不備がないかを窓口で確認してもらい、問題なければ申立は完了です。

この時点での書類の確認は、必要な書類がそろっているかといった確認になるため、
あくまで申し立てが受け付けられた状態です。
(2)裁判官が申立書や診断書をもとに書面審査を行う
提出した書類をもとに、提出した書類をもとに、申立人が戸籍の性別変更の条件をみたしているかを裁判官が審査します。前の項目で触れていた「性別適合手術をしたことの証明」が精神科医の診断書で足りるか否かも、この段階で判断されます。
また、必要に応じて申立人が呼び出され、提出された書類や、書類以外の条件について直接事情聴取が行われる場合もあります。

僕の場合は直接の事情聴取はなく、申し立て後しばらく待っていたら、直接通知書が届きました。
ちなみに今回の項目からははずれますが、名前の変更手続きの際は電話での事情聴取がありました。
(3)裁判官が性別を変更するか否かを最終判断する
裁判官が提出書類や事情聴取の内容を踏まえ、最終的に戸籍の性別変更の可否を決定します。
(4)家庭裁判所から役場へ変更の申請が届き、新戸籍が編製される
(3)で家庭裁判所から役場へ「戸籍の変更をしてください」という申請が届き、新しい戸籍が編製されます。元の戸籍の性別だけが変わるのではなく、申立人を筆頭者とする新戸籍が編製されます。なお、戸籍の性別変更は裁判所と役場が進めるため、(1)の後に申立人が直接何か手続きを行う必要はありません。

ちなみに、名前の変更手続きの際は戸籍の性別変更とは異なり、
家庭裁判所へ「名の変更許可申立」を行うところは同じですが、変更が認められた後は
自分で役所へ変更の届出を行う必要があります。
(5)申立人に「戸籍の性別変更の通知書」が届く
申請から約1~2ヶ月後に自宅に「戸籍の性別変更の通知書」が届き、これで戸籍の性別変更は完了となります。学校や職場でも性別を変更する手続きが必要になる場合もあるので、そちらも忘れず行いましょう。
ホルモン治療は、性別適合手術後の身体の状態により、投与量や頻度などを術前から変更する場合もあるので、かかりつけの先生と相談しつつ治療を継続させていきましょう。
・戸籍の性別変更の申し立ては事情聴取が行われる場合もある
・申し立てが認められた後は通知書を待つだけでOK
・戸籍は新しい戸籍が作られる
戸籍の性別変更のこれから

ここまで読んでくださりありがとうございました!
戸籍の性別変更について、少しでも理解いただけたようなら嬉しいです。
最後に、戸籍の性別変更に関するある事例についてお話したいと思います。
令和5年10月25日の事例により、戸籍の性別変更条件⑤「生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること。」という項目について疑問視する声が増え、性別適合手術(生殖器をなくす手術)はせずとも戸籍変更ができる例が増えつつあります。
性別適合手術は身体的にも金銭的にも負担になるので、そういった形で特例が認められることは喜ばしいことだと思います。
ただ、戸籍の性別変更はゴールではなく、あくまで身体の違和感を治療でなくしていった先(途中)にあるものだと僕は思います。いつか⑤の条件がなくなって、「戸籍を変えるために必要な治療」が減ったとしても、本人が身体の違和感をなくすのに必要だと思ったのなら、それは間違いなく「必要な治療」です。
また単に現在の条件を「厳しすぎる」「憲法に違反している」と否定するのではなく、どうして現在の条件(生殖機能の有無)が設定されたのかについて考えることも、当事者・非当事者関係なく大切だと改めて感じました。
戸籍の性別変更の条件や治療法など、今後も絶え間なく変化していくと思いますが、
b-LIGHTのライターとして正しい情報を皆さんにお届けできるよう頑張りたいと思います!
それでは、また次回の記事でお会いできたらうれしいです!
監修:はりまメンタルクリニック 針間克己医師
参考文献:針間克己(2025)『プロブレムQ&A 性別不合って何?[理解を深めるため
に]』(緑風出版)
おすすめ書籍
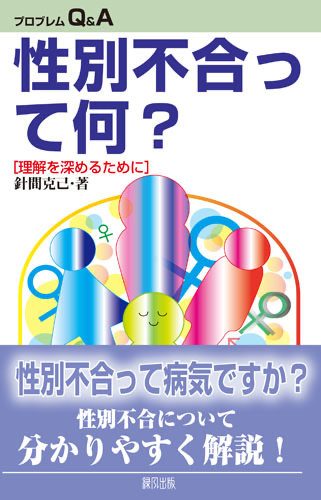
プロブレムQ&A 性別不合って何?[理解を深めるために]
針間克己[著]